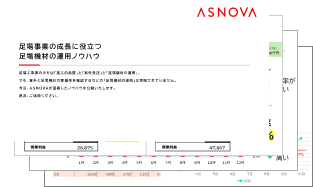単管足場とは?主要部材や組み方、その他足場との違いを解説
足場のTIPS

単管足場とは?主要部材や組み方、その他足場との違いを解説いたします。
足場の中でも、組み立ての柔軟性が高く狭い場所でも設置可能といったメリットをもつのが単管足場です。一方で、組み立てに掛かる時間がかかることや他の足場に比べ強度が劣るという点も事実です。
そこで、単管足場とは何か、枠組み足場のメリットやデメリット、組み立てに使う部材について解説していきます。
単管足場とは
単管足場とは、直径48.6mmの鋼管で作られた単管パイプにクランプという金具を接続し、さらにボルトで固定して組み立てる方法を取る足場のことです。
特徴としては、単管パイプとクランプを軸に、足場の形状を柔軟に変化させることが出来るので、狭い場所でも足場を組むことが可能となります。
主に低層の外壁塗装用の足場として使用されます。
デメリットとしては、単管パイプをボルトで固定していく必要があるため、他の足場に比べて組立てと解体にやや時間がかかることや、強度があまり高くないという点が挙げられます。
一方で足場の形状の自由度が高いため、他の足場が使えない狭い場所でも組み上げることができることや、組立て自体は比較的簡単で、部材はホームセンターでも購入できるという点はメリットといえます。
単管足場の労働安全衛生規制について
<労働安全衛生規制 第571条>
一 建地の間隔は、けた行方向を一・八五メートル以下、はり間方向は一・五メートル以下とすること。 二 地上第一の布は、二メートル以下の位置に設けること。 三 建地の最高部から測つて三十一メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の二分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。 四 建地間の積載荷重は、四百キログラムを限度とすること。
>全国仮設安全事業協同組合「足場に係る改正労働安全衛生規則等について」
労働安全衛生規制 第571条に基づく単管足場の構成
単管足場の構成に関しては、上記の通り労働安全衛生規則第 571 条に次の規定があるので、それを順守し組み立てを行わなければいけません。
- 建地の間隔は、けた行方向を 1.85 m 以下、はり間方向を 1.5 m 以下とする。
- 地上第一の布は、2 m 以下の位置に設ける。
- 建地の最高部から測って31mを超える部分の建地は、鋼管を2本組とする。ただし、建地の下端に作用する設計荷重が、当該建地の最大使用荷重を超えない場合は、2本組の必要はない。
- 建地間の積載荷重は、400kgを限度とする。
単管足場の主要部材
基本構造部材は、単管パイプ・固定ベース・クランプ・単管ブラケット・足場板・ジョイントです。
- 単管パイプ
単管パイプとは、直径48.6mmのパイプの形をした鋼管。
単管パイプは別名で「単管」や「パイプ」と言われています。
- 固定ベース
地上に設置して、足場を固定する資材です。
- クランプ
単管パイプや足場で使う資材に使うつなぎ金具。
主に、直交クランプと自在クランプを使います。
- 単管ブラケット
ブラケットは水平材、斜材、垂直材および建地へ取り付けるための2個の取り付け金具より構成された資材です。形状により、固定型、伸縮型、張り出し型に分類されます。また、ブラケットの先端は足場板等の脱落防止用の脱落防止板または手すり柱受けを有するものとします。
- 足場板
足場板とは、工事現場で作業する際の作業床のことです。
高所で作業する際に持ちいられることが多く、作業員の体重を支えられる必要があるため、高い強度が求められる。
足場板の材質にはスチール、アルミ、合板、杉などがあります。
- ジョイント
上下の建枠と建枠を繋げる資材。
ジョイント/ピンの種類は主に「ヤマトピン」「連結ピン」「オートピン」の3つがあります。
単管足場の組み方
では、単管足場の組み方を順を追ってご紹介いたします。
- 敷板・敷角の設置 足場が滑ったり沈んだりすること防ぐために、支柱と地面との接地面に敷板や敷角を設置します。
- 支柱の組み立て 敷板や敷角の上に単管ベースを基準にし、縦方向の単管パイプの支柱を垂直に組み立てていきます。 支柱と支柱の連結には根がらみを使用します。
- 枠組み 単管パイプ同士をクランプなどの緊結金具を使い枠を組んでいきます。 枠組みの安定性を保つためクランプの締め付けトルクは標準値にて、均一に締めるようにしめましょう。 枠が組めたら足場板を渡して単管に固定します。
- 壁繋ぎで固定 単管を壁つなぎを使って固定していき、筋交いを設置すると倒壊防止の効果があるので、筋交いを枠外へ斜めに固定するようにして補強しましょう。
単管足場のその他足場との違い
足場には、パイプや丸太などを使って組み立てる「組立足場」と、屋上や梁などから吊るされる「吊り足場」の2種類があります。
さらに組立足場には、枠組足場のほかに、手摺や筋交を支柱の緊結部にくさびで緊結する「くさび緊結式足場(ビケ足場)」と、単管パイプにクランプなどの基本部材を組み立てる「単管足場」があります。
これら3つの組立足場の特徴の違いは、単管足場は低層の外壁塗装用に、くさび緊結式足場(ビケ足場)は中層建築工事用ないし高層建築物の外壁の塗り替えなどに使用されるのに対し、枠組足場は建築物の外壁面に沿って設置されることです。
まとめ
今回は、単管足場とは何か、単管足場の組み立てに使う資材などををご紹介いたしました。最後に単管足場の特徴についておさらいしておきましょう。
- 枠組足場を設置できない狭いスペースや低層の外壁でも利用可能
- 主に使う資材が単管パイプとクランプのため、組み立てが簡単。
- 単管パイプとクランプを駆使することで 柔軟に足場の形状を変化させることが出来る
- 資材がホームセンターなどで簡単に購入できる。
単管足場は、ホームセンターなどで簡単に購入できるため、DIYをされる方にも簡単に取り扱いができるのが特徴です。単管足場を使えば自宅のサンルームや物置小屋なども簡単に作ることもできます。オシャレな空間作りができるのも足場の魅力の一つですね。
なお、ASNOVA公式の足場販売サイト「ASNOVA市場」では、単管足場の組み立てに使う資材の他に様々な商品を取り扱っておりますので、是非ご覧ください!