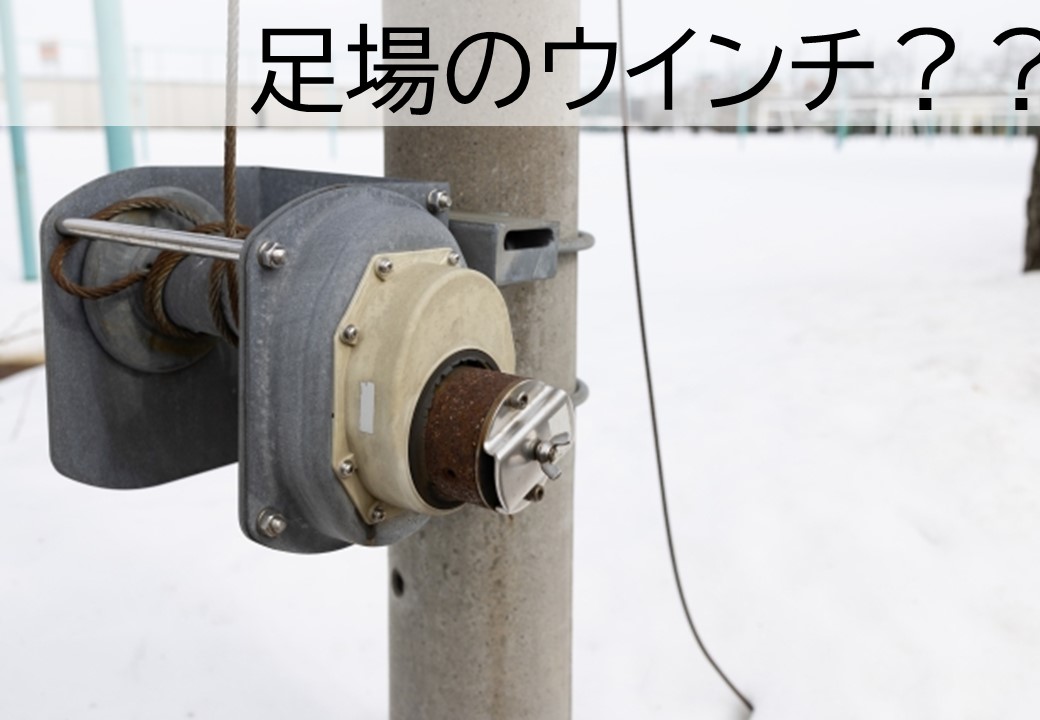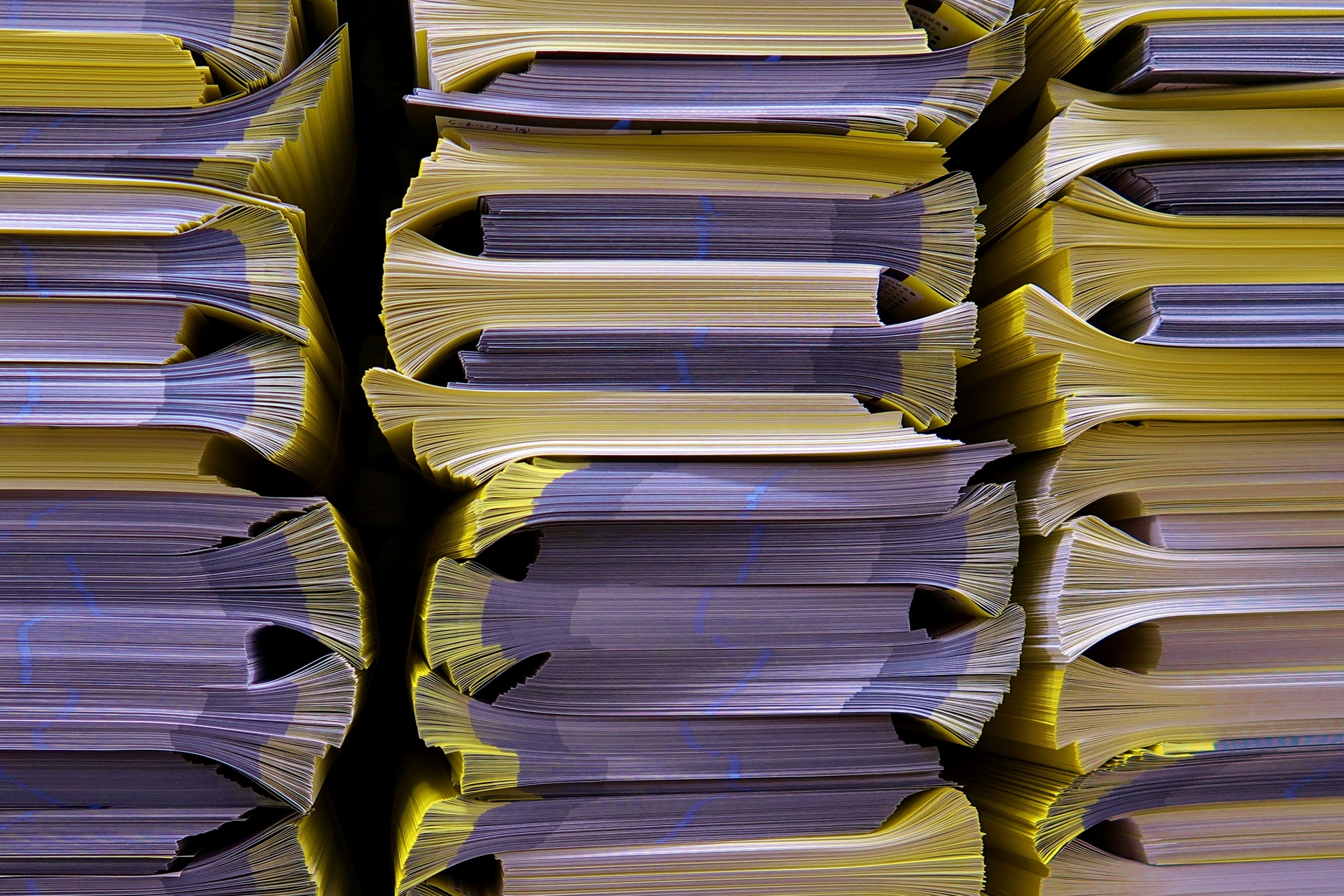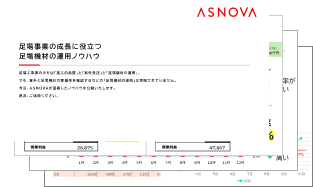くさび緊結式足場とは?9つの主要部材やビケ足場との違いも解説
足場のTIPS

くさび緊結式足場とは?特徴と足場の組み立てに使う資材をご紹介
工事現場で利用される足場には、組立て足場と吊り足場の2種類に大別され、主にくさび緊結式足場、枠組足場、単管足場、ブラケット一側足場、張出し足場、吊り足場、吊り棚足場、丸太足場などの種類があります。
今回は、組立て足場のくさび緊結式足場について、特徴や組立てに使う資材をご紹介いたします。
目次
くさび緊結式足場とは?
くさび緊結式足場とは、一定間隔に緊結部を備えた鋼管(鉄パイプ)を建地(支柱)とし、手摺や筋交等の左右にある「くさび」部分を支柱の緊結部である「コマ(ポケット)」にハンマーで打ち込んで緊結する構造の足場を指し、ハンマー1本で簡単に組み立てが出来ます。
以前は木造家屋などの低層住宅工事用の足場として多く使用されていました。
しかし、最近では一般住宅、中高層建築、狭小地などで使用されることが増えてきています。
メリットは、組立てや解体が簡単で、複雑な形状の建物にも対応できることです。さらにコストパフォーマンスにも優れていますが、場所によっては設置できないこともあります。
くさび緊結式足場の特徴とは
1.とにかく軽くて簡単に組み立てができる
くさび緊結式足場は柱・踏板・手摺・先行手摺等の部材をハンマーひとつで簡単に組み立てることのできる足場です。
各部材がシンプルなつくりで軽量なので組み立てが簡単で、最低2名の作業員で行うことができます。
限られた人手の中で効率よく組むことができる材料なので、コストパフォーマンスがとても良いということですね。
単管足場のように水平にクランプを組んでいくような位置決めや、ポルトで締める等の細かい部品を扱う難しい工程もありませんので、スムーズに作業を進めることができます。
2.コンパクトに積めて運送費がお得! 積み下ろしもラクラク
部材のつくりがシンプルなことで、まとめて材料を運ぶ時もコンパクトに結束ができて保管に場所を取りません。
現場によっては敷地の狭いところに保管しなくてはいけない状況もありますので、コンパクトに積み下ろしでき、場所を取らずに置けることが大切になってきます。
また、現場への輸送効率も良く、運送にかかる費用だけでなく業務の効率化・労働時間の短縮も実現できます。
重量的にも軽い形状になっていますので、より多く積載することができ輸送費のコストを大幅にカットすることができます。
さらに、積み下ろしの負担が少なく、運送のトラックの台数の削減・部材のトラックへの積み下ろし・搬入搬出等の作業工程をスムーズに進めることが可能です。
くさび緊結式足場の主要部材
基本部材構成は、ジャッキ、支柱、手摺、踏板、ブラケット、筋交、鋼製階段、先行手摺、壁当てジャッキです。
- ジャッキ
足場の最下部に使用して上下の高さを調節する資材。
ジャッキは足場を支える「足」の役割があり、仮設足場の安定性を高める重要な資材です。

- 支柱
支柱はコマという緊結部が一定間隔ごとについている鋼管(建地)のことです。
支柱下部は、左右の高さを水平に調整するために一般的にはジャッキに挿入します。

- 手摺
手摺はコマに緊結するためのくさびが左右についている鋼管です。
手摺のクサビを支柱のコマに挿して使います。
これにより、支柱に固定されて安全に作業を行うことができます。
また、踏板や階段などを取り付けるためにも使います。

- 踏板
両側に計4つのフックがついており、網状の足場として使う資材です。
フックはブラケットや手摺に掛けます。

- ブラケット
ブラケットは水平材、斜材、垂直材および建地へ取り付けるための2個の取り付け金具より構成された資材です。形状により、固定型、伸縮型、張り出し型に分類されます。

- 筋交
筋交(すじかい)とは、地震や風などで倒れたりしないように、柱と柱との間に斜めに入れる資材です。
地震の横揺れや台風の際の強い横風など横から掛かる圧力に対応しなければなりません。耐震・耐風対策はもちろんですが、足場の強度を高めるために補強材である筋交が必要になります。

- 鋼製階段
足場に上がるための鉄製の階段です。
上部についたフックを単管パイプに引っ掛けて設置します。

- 先行手摺
「手摺」「筋交」の役割を行うことができる資材です。
足場の組立・解体時において常に先行して手すりが設置できるため、最上層でも手すりがある状態で作業ができるので、墜落の防止に役立ちます。
- 壁当てジャッキ
足場が内側に倒れないように設置する資材です。
使用の際は、ジャッキホルダーと一緒に使います。
- アンダーベース
パイプジャッキとセットで使用。足場の沈下を防ぐ目的で使います。
枠組足場/その他足場との違い
足場には、パイプや丸太などを使って組み立てる「組立足場」と、屋上や梁などから吊るされる「吊り足場」の2種類があります。
さらに組立足場には、枠組足場のほかに、手摺や筋交を支柱の緊結部にくさびで緊結する「くさび緊結式足場(ビケ足場)」と、単管パイプにクランプなどの基本部材を組み立てる「単管足場」があります。
枠組足場とは
建枠と呼ばれる基本部材をボルトや番線を使って組み立てていきます。
枠組足場は、資材の種類が多くそろっているため、資材を組み合わせて細かいところまで対応でき、現場の条件にあわせた足場を作ることができます。しかし、特殊な部材や種類が多いことで、組み立てるための知識や経験が必要になります。 枠組足場の一番の特徴は足場強度が高いところです。
大規模工事の組み立て方は建枠を事前にいくつか組み立ててから、クレーンで積み上げていきます。 そのために広いスペースが必要なので、狭い現場での作業には向かないことが多いです。
単管足場とは
単管と呼ばれる直径48.6㎜のパイプとつなぎ止め金具のクランプを組み合わせて作る足場です。 単管とクランプは置いておく場所も取らず、狭いスペースの現場や低層の外壁でも利用可能です。一戸建てや細い路地に面した土地でも足場を組むことができます。
強度や安全面については他の足場より劣り、高所のビル等での工事には使用できないケースもあります。 単管足場は部材の付属品が少なく、自由に組むことができますが、クランプの位置決めや組み立てに時間がかかります。
これら3つの組立足場の特徴の違いは、単管足場は低層の外壁塗装用に、くさび緊結式足場(ビケ足場)は低中層建築工事用ないし45m以下の高層建築物の外壁の塗り替えなどに使用されるのに対し、枠組足場は強度が高いため、大型案件に設置されることが多いです。
まとめ
今回は、くさび緊結式足場とは何か、組み立てに使う資材などをご紹介いたしました。最後にくさび緊結式足場の特徴についておさらいしておきましょう。
- ハンマー1本で組み立て、解体が可能。
- コンパクトに結束できるので、輸送コストが下げられる。
- 組立が簡単でほかの足場より約20%作業時間を短縮できる。
- 亜鉛メッキ処理されているので、錆に強く耐久力がある。
- 主に、低中低層建築工事用に使用されている。
- サイズ規格や形状によってさらに4つのタイプに分類される。
ASNOVA編集部からのコメント
ASNOVAがレンタルしている足場は【くさび緊結式足場】と言って、とにかくとても軽くて誰でも組み立てができる足場機材です。部材のつくりがシンプルなことで、まとめて材料を運ぶ時もコンパクトに結束ができて保管に場所を取りません。より詳しい情報についてはお気軽にお問い合わせください!